コースタイム(休憩時間を含む) | ||
登山日 2006年07月23日 |
||
|
『登り 4時間10分』 銀泉台 05:30 第二花園 06:30 駒草平 06:45 第三雪渓 07:05 赤岳 07:52 白雲岳 09:40 |
||
|
『下り 3時間15分』 白雲岳 10:00 赤岳 10:55 赤岳発 11:15 駒草平 12:20 銀泉台 13:15 |
||
|
【ひとくちメモ】
登山道の傾斜も急ではなく、子供や初心者でも経験者が同行すれば比較的簡単に登ることが出来るコースです。 ただ、8月中旬までは、登山道に
雪が残っていて、場所によっては堅く凍り付いているので、足を滑らせないように注意が必要です。 白雲岳までは、銀泉台から歩行距離で約往復15 キロとなっています。 銀泉台は、夏から秋にかけて非常に人の出入りが多く、駐車場がすぐ一杯となりますので、駐車場への到着は早いほうが良いでしょう。 銀泉台には比較的清潔なトイレがありますので、駐車場での車中泊が可能です。 以前宿泊可能だった銀泉台ヒユッテは、2006年度シーズンから残念ながら宿泊が出来なくなりました。 このコース、秋には紅葉見物の登山者以外の観光客が増えるため、例年一般車両の交通規制が行われます。 |
||
|
7月の海の日を挟んだ三連休でしたが、天気が悪く山登りは残念ながら断念。 翌週は当初好天の予報でしたが、週末が近づくに従って段々お天気が下り坂となってしまいました。 今回を逃すと、お花のハイシーズンが終わってしまうので、天望は期待せず、お花狙いで大雪山の「表銀座」銀泉台〜白雲岳を目指すことにしました。 今回のメンバーは、いつものMarikka、Tutumiさん、そして私の3名です。 前日、大雪ダムの駐車場に車中泊でしたが、夜半から激しい雨が降る不安定なお天気です。 |
|||
 |  |
||
|
午前4時過ぎに大雪湖ダム駐車場を出発し、午前5時15分に銀泉台に到着です。 途中、車道から平山方面の山並みが朝焼けをバックに雲海の上に顔を出していて、幻想的風景が広がります。 銀泉台駐車場には沢山の車が停まっていましたが、今回はわりと楽に駐車が可能でした。 銀泉台に車中泊した人を含め、既に沢山の登山者が出発の準備をしています。 お天気は、空が比較的明るく、青空が微かに顔を出しています。 今年から銀泉台の宿泊書が廃止となりましたが、入山届けの小屋には常駐している人がいるらしく、以前のとおり小屋の中の名簿に記入して登り始めます。 登山口のトイレは、一応管理されているようで、比較的清潔に保たれ、手洗い場の水も何とか出る状態でした。 |
|||
 |  |
||
|
いつもなら遠く感じる駒草平ですが、今日は体調が良いせいか、難なく到着です。 駒草平の前後から、お花の数が増えて、登山道の両側には数え切れない程の高山植物が咲き乱れています。 この季節は、以前にも何度か訪れていますが今回のお花の数が一番かもしれません。 肝心のコマクサは既に少し盛りを過ぎていて、色も例年より薄めになっていましたが、登山道の両側に咲き乱れるように咲いています。 駒草平のコマクサも一時は数が少なくなって心配されましたが、監視員やボランティアの方々の努力で徐々に回復しているようです。 駒草平を過ぎると、第3雪渓が見えてきます。 |
|||
 |  |
||
|
第3雪渓は、雪解け水が登山道の上を流れ落ちており、登山道が滝のようになっていました。 元々岩が多い場所なので、水が流れていても比較的安全に登ることが出来ました。 第3雪渓と第4雪渓の間の平坦な場所は、第4雪渓付近からの雪解け水が溜まり、まるで沢のようになっていました。 登山道の窪みを綺麗な雪解け水がゴウゴウと流れています。 登山靴で歩くことが出来ないような流れではありませんが、登山靴を濡らさないように慎重に進みます。 第4雪渓の下には、凄い数のお花畑となっており、斜面の大部分がお花で埋まった状態になっています。 今年は昨年より少し雪渓が小さいような気もしますが、僅かに残った雪渓でショートスキーを楽しんでいる強者がいました。 |
|||
 |  |
||
|
第4雪渓を順調に登り切り、銀泉台から約2時間30分で赤岳到着です。 赤岳は、相変わらず凄い人出で、せっかく期待していた黒岳、旭岳方面の展望も雲に隠れて見えないので、休憩を取ってすぐに白雲岳方面に向かいます。 途中少しは回復していたと思われたお天気ですが、ここに来て少し雲が増えてきたようです。 あまり視界が良くないなかを、登山道の黄色のペンキを見逃さないように慎重に進みます。 赤岳を過ぎるとめっきり登山者の数が減ってしまいます。 比較的平坦な登山道を、両側のお花を楽しみながら進むと、やがで緑岳への分岐、続いて白雲岳避難小屋へ続く分岐が現れます。 白雲小屋への分岐には、白雲に向かった登山者が置いていったザックが残されていました。 |
|||
 |  |
||
|
白雲岳に向かう道の両側には無数の高山植物が今を盛りと咲乱れています。 大きい花も多いのですが、目を懲らさなければ見逃してしまうような小さな花を付けた高山植物も多く、少し疲れが出てきた体を励ましてくれます。 綺麗な花を見つけては登山道にしゃがみ込んで写真を撮りながら進むので、少しペースが落ちてきました。 |
|||
 |  |
||
|
白雲岳がだんだんと近くなり、登山道に岩が多くなり始めた頃、一瞬天気が回復し、よく登山の雑誌のグラビアページを飾っている名物の残雪が筋状に残る大パノラマが見えましたが、直ぐにガスに覆われてしまいました。 |
|||
 |  |
||
|
花に見とれながらガスの中を進むと、前方に白雲岳山頂の標識が見えてきます。 山頂には、既に何人かの登山者もいるようで、その姿が見え隠れしています。 白雲岳山頂直下の岩場を手足総動員で慎重に登り詰めると、1年ぶりの白雲岳山頂です。 生憎山頂は、薄いガスに包まれ、期待したパノラマを今年も見ることが出来ませんでした。 比較的早く山頂に到着したので、山頂でコーヒーと軽い食事を取りながら20分程天気の回復を待ちましたが、結局ガスは晴れず、下山することにしました。 帰りは、ゆっくりとお花を撮りながらの下山の予定でしたが、第4雪渓下付近から雨が降り始め、大急ぎでの下山となりました。 天気には恵まれませんでしたが、沢山のお花には恵まれ、大満足の一日となりました。 |
|||
登山道でみかけたお花たち。 |
|||
 |  |  |  |
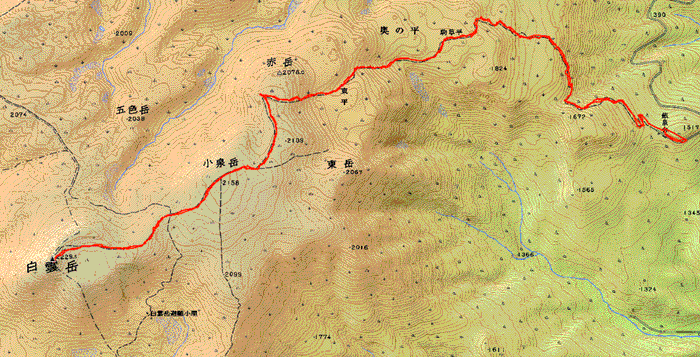 銀泉台からのGPSログトラック |
|||